



サステナビリティ
Sustainability as the only path
創造と革新で、人と社会、地球の「きれい」に貢献し、すべてのいのちが調和するこころ豊かな未来をめざします。
In Action
サステナブルな社会を実現するために、花王が取り組んでいる活動を紹介します。
Kirei Lifestyleとは、こころ豊かに暮らすこと
花王は、生活者の持続可能なライフスタイルを送りたいという思いや行動に応えることをめざしています。生活者が求める暮らしを Kirei Lifestyle と呼び、その実現に向けて、ビジョン、コミットメント、アクションからなるESG戦略「Kirei Lifestyle Plan」を策定し、社会のサステナビリティに貢献する取り組みを進めています。
花王のESG戦略とアクション
花王は、1887年の創業以来、消費者起点を基本に企業活動を展開してきました。
消費者視点でモノづくりを推進することは、花王の企業理念の礎です。絶えざる革新への挑戦、細部にまで配慮した製品の開発、そして一歩進んだ提案や取り組み、それらすべてが、消費者のニーズに応えることをめざしています。
花王のESG(環境・社会・ガバナンス)戦略であるKirei Lifestyle Planは、消費者起点のもと、世界中の人々の「持続可能なライフスタイルを送りたい」という思いや行動に応えることをめざして策定されました。こうした、人々が望む暮らしを、「Kirei Lifestyle」と定義し、こころ豊かに暮らすことができるよう、事業のあらゆる面で革新を進め、さらなる社会への貢献をめざしてまいります。
自然環境への取り組み

花王の事業は、製品のライフサイクル全般にわたって、地球上のさまざまな生態系、生物の多様性がもたらす豊かな恵みによって支えられています。そのため、花王は、原材料を選ぶところから、廃棄・リサイクルまで、すべての段階で自然環境に配慮したモノづくりに取り組んでいます。
社会貢献活動
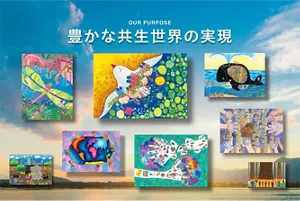
「豊かな共生世界の実現」をめざし、持続可能な社会のために、事業活動と両輪で社会貢献活動に取り組んでいます。




















