花王のよきモノづくりの系譜
古今東西の清浄文化史と花王のよきモノづくりの変遷をご紹介します。
話題を呼ぶ広告手法
花王は「いいものをつくるだけでなく、その良さを人々に知ってもらわなければならない」という使命感から、初代「花王石鹸」を発売した1890年代より広告宣伝に力を入れてきました。
初代「花王石鹸」の発売1年目は、事業利益の44%を広告費にあてました。実直に、商品の良さを訴求しつづけること。花王が創業以来、守りつづけているポリシーです。
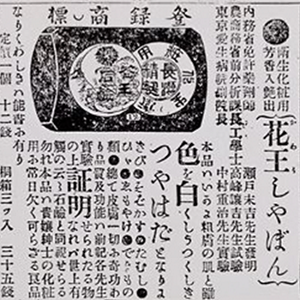
「花王石鹸」発売時の新聞広告。全国紙に広告を出すことで、認知を広げました。(1890年)

建物の壁面に大型看板を設置するなど、花王は街中にも次々と広告スペースを開拓していきました。(1910年)

鉄道沿線に設置された広告を「野立て看板」と言います。今も車窓から見られますが、その第1号が「花王石鹸」でした。(1925年頃)
生活者の目で家事を科学する
生活者のニーズに応えるため、花王は1934年(昭和9年)に「家事科学研究所」を設立しました。「婦女子の末技」と軽んじられてきた家事全般を科学的に見直し、その合理化と能率性を向上させることを目的にした、消費者研究のパイオニア的研究所です。

お洗たく講習会の様子(左) 機関紙(月刊)「家事の科学」(右)
この研究所は、一般消費者向けに工場見学や商品の講習会などを開催し、家事に関する情報や知識を提供するとともに、一般家庭を訪問して家事の実態をリサーチし、分析した結果を商品開発に活かしました。生活者の視点に立ったモノづくりの姿勢は、現在の花王に継承されています。
清浄文化は石けんを超えて
「花王石鹸」の登場は1890年(明治23年)。それから90年後の1980年(昭和55年)に、ペースト状の洗顔料「ビオレ」を発売しました。石けんから始まった花王が、その石けんを自ら否定するという意味でも画期的な製品でした。1985年(昭和60年)には社名も「花王石鹸」から「花王」に変更しました。技術革新によって、新しい生活習慣を提案する商品が多数生まれました。
石けんからビオレヘ



洗顔は「ビオレ」、ボディーは「ビオレu」。
1970年代まで、洗浄料の主役は石けんでした。そんな中、花王はより肌にやさしい洗浄剤をめざして、石けんよりも皮膚の刺激が少ない洗浄基剤「モノアルキルフォスフェート(MAP)」を開発します。このMAPを採用した洗顔料「ビオレ」や全身洗浄料「ビオレu」で、花王は新しい洗浄習慣を提案しました。
ライフスタイルを変えた製品

1970年
メリット
フケや頭皮のかゆみに悩む人のために開発され、ヘアケア文化の向上に貢献しました。

1979年
ロリエ
不織布と吸水性ポリマーの技術を結集した花王初の生理用品で、生活者に「安心」「快適」を提供しました。

1982年
ソフィーナ
皮膚科学に基づいた化粧品で、メイクを“洗い流して”落とすスタイルや、毎朝のお手入れで紫外線を防ぐ習慣を提案しました。

1983年
メリーズ
「高吸収」「ぬれてもサラッと」「モレを防ぐ」吸水性ポリマーと不織布の技術で、朝までぐっすり眠れるおむつを実現しました。
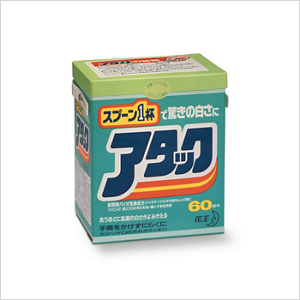
1987年
アタック
繊維の奥の汚れに働きかける酵素の技術で、洗たく用洗剤を劇的にコンパクト化。「スプーン一杯で驚きの白さに」を実現しました。

1994年
クイックルワイパー
複合不織布により、フローリング時代に対応したサッと立ったままできる床掃除の新スタイルを提案しました。




